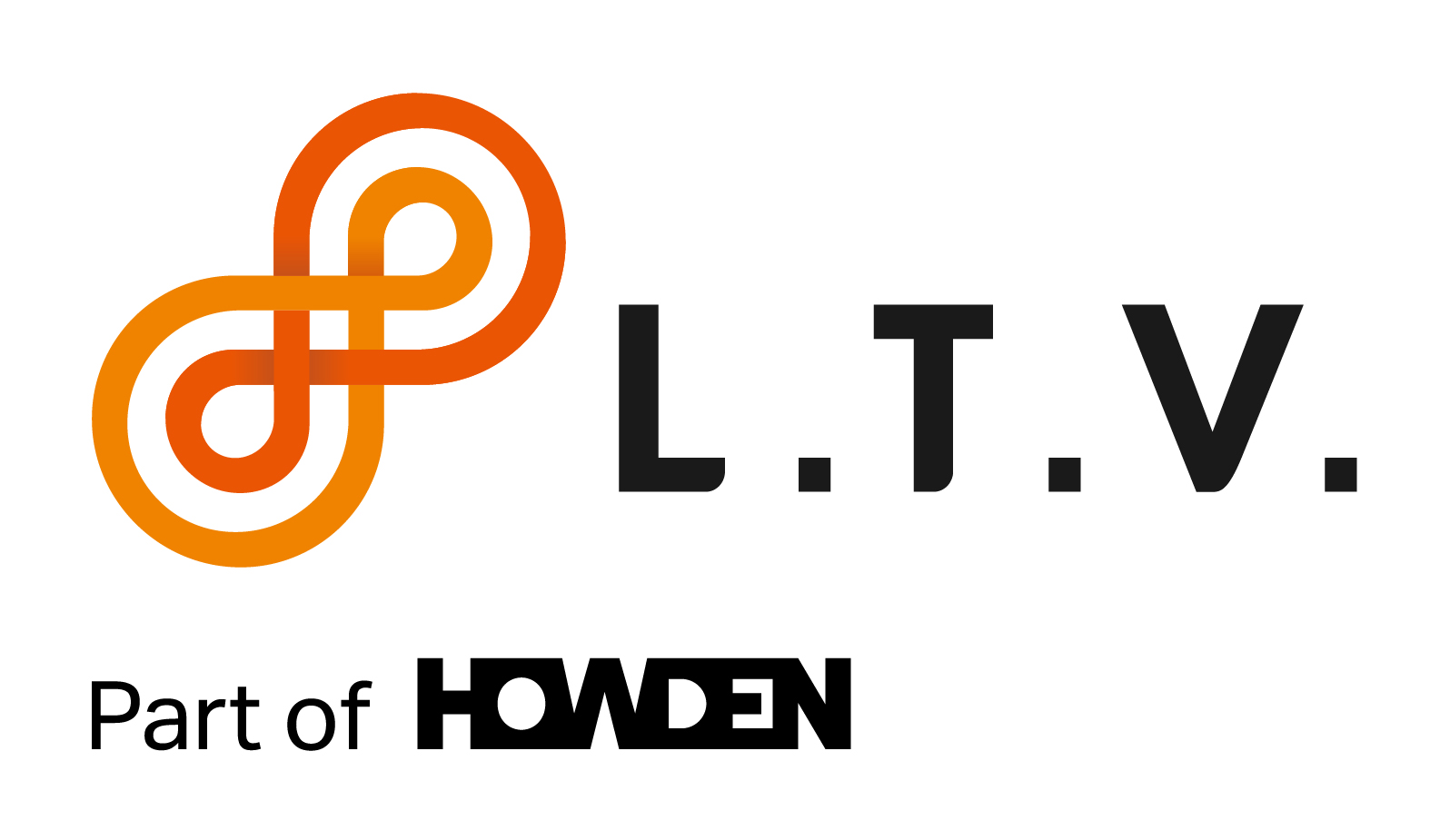著作者:our-team/出典:Freepik
様々な変化に柔軟に対応し迅速な判断を行う上で、管理職(マネージャー)の存在は欠かせません。
これを証明するのがGoogle社による実験結果です。
(参考: Google社 Project Oxygen:https://rework.withgoogle.com/jp/subjects/managers )
Google社では2002年と2008年に「全マネージャ―を廃止」する試みを実施しました。2度の実験結果から、Googleにとって必要なマネージャー像が浮き彫りになったとされています。その後、Googleでは優れたマネージャーを特定する10個の要件をまとめ、マネージャーに対するサポートも行っています。
しかし日本では、若手に対しては手厚い研修制度が整っているものの、管理職者に対する能力開発の制度が整えられている企業は多くありません。
本コラムでは、コラム「なぜ今急増?管理職層に対する教育を見直した方が良い5つの理由」で取り上げた課題ごとに効果的な対策をご紹介していきます。
管理職の能力を最大化させるために「今」必要な5つの対策
対策案1)新しいリーダーシップのあり方を身につける
対策案2)心理的安全性を確保し、コミュニケーションを取りやすい環境を整備する
対策案3)ジェネレーションギャップを受け入れ、理解を深める
対策案4) 実行可能な指導・育成スキルを身につける
対策案5)隙間時間を活用できる”制度の整備”と”アウトプットの仕組み化”
“課題に応じた研修”を通して解決のヒントを手に入れよう!
【対策案1】
1)急速なビジネス環境の変化→新しいリーダーシップのあり方を身につける
急速なビジネス環境の変化へ柔軟に対応する強い組織を創るために、大きく2つのリーダーシップスタイルに目を向けることをお勧めします。
変化の激しい環境では、固定化されたリーダーシップスタイルではなく、状況に応じて柔軟に対応する「 適応型(アダプティブ)リーダーシップ」が管理職に求められます。なぜなら、組織が”変化する環境”へ適応するために、自分たちの物の見方や考え方の転換を促し、行動自体を変えていくために必要となるからです。例えば上司には、デジタル変革が進む中で、テクノロジー活用に対する理解を深め、部下と共に学びながら新しい働き方を推進する姿勢などが求められます。
特に現代では、トップダウン型のリーダーシップではなく、チームメンバーと協力しながら価値を生み出す「共創型リーダーシップ」も重要です。多様な意見を尊重し、部下の主体性を引き出すことで、組織全体の適応力を高めることができます。例えば、心理的安全性の高い職場環境を作り、部下が自由に意見を言える文化を醸成することが、イノベーションや組織の成長につながります。
いずれのリーダーシップでも言えることは、自分以外の人が抱く信念や価値観、夢や希望、才能、強みなどを理解し、受容・共感できる能力が必要不可欠だということです。そのためには、様々なケースワークを取り入れ、内発的な気づきを多く得られる研修を取り入れると良いでしょう。
【対策案2】
2)部下とのコミュニケーション不足 ⇀ 心理的安全性を確保し、コミュニケーションを取りやすい環境を整備する
“聞く姿勢”には、相手とのコミュニケーション意思が反映されます。
例えば、以下のようなシチュエーションであなたはどのように感じるでしょうか?
————————–
あなたは、現在進めている業務の進捗を報告しようと上司の席を訪れました。
「お時間よろしいでしょうか。業務の進捗の報告をしたいのですが」と声をかけると、「大丈夫だよ、どうぞ」と返事が返ってきました。
A:上司はパソコン操作をしたままで、こちらを向く気配はありません。
B:上司は手を止めると椅子をくるっと回転させて、こちらを向きました。
どちらの方が「話を聞こう」という意思を感じるでしょうか。
————————–
多くの方が、Bに対して話を聞こうという相手の意思を感じるのではないでしょうか。
Aに対しては、「忙しいのかな?」と思う部下もいれば「自分の報告はそこまで重要視されていない」と受け取る部下もいるでしょう。
ただ、多くの場合、管理職本人は意図せず、無意識的にAのような対応を行っている可能性があります。しかし、このような状態が何度も続くと、部下は「どうせ報告しても真剣に聞いていないから」と感じ、報告の頻度が下がり、コミュニケーションを取る機会も少なくなってしまいますし、組織の心理的安全性も低下してしまいます。
まずは「アクティブリスニング研修」を実施し、部下の話を傾聴し、共感を示すスキルを身につけることをお勧めします。
当社がご提供する研修では、知識の習得とロールプレイを用いた実践トレーニングを行います。脳科学の観点からアクティブリスニングを行うことでどういった変化が生まれるのかを理解し、「うなずき」「相槌」「バックトラッキング」という傾聴の3要素と意図や考えを引き出す質問スキルをトレーニングします。部下の発言に対し「質問」「要約」「フィードバック」の3ステップで応答する習慣を身につけられる内容を取り入れると、即日業務に活かすことができます。
管理職は、周囲を変えようとするのではなく、自身が変わることで組織に大きなインパクトを与えます。結果的に、職場の心理的安全性が高まり、円滑なコミュニケーションが取れるようになります。アクティブリスニングを取り入れることで、管理職は一方的な指示命令ではなく、双方向の対話を意識するようになります。
【対策案3】
3)ジェネレーションギャップの拡大 ⇀ ジェネレーションギャップを受け入れ、理解を深める
意思疎通が難しく感じる背景の一つに世代間ギャップがあります。時代背景や育ってきた環境の違い、経験の差などから価値観が異なるために生じる問題です。例えば「物」に対する考え方です。様々な新商品が発表されて「新しい物」を求めていた時代と、生まれた時から様々な物に囲まれて過ごしてきた時代では、物欲に対しても違いがあって当然と言えるのではないでしょうか。
このような違いについて理解を深める策として、世代ごとの価値観の違いと、それらを生み出した社会的背景について学び、相手の視点・価値観を理解し、適切なマネジメントを行うための「ジェネレーション理解促進研修」を実施してみてはいかがでしょうか。
具体的には、心理学を活用したケーススタディやロールプレイング、ワークショップを実施し、異なる価値観を受容する姿勢が学べるものが良いでしょう。当社の研修では、受講者と若手の時代的背景の違いやビジネス環境の違いを具体例を用いて学習します。更に、ディスカッションやワークを通して思考を整理し、職場で活かすことのできるコミュニケーションスキルと共に学習する内容となっています。
また、若手社員との対話の場を設け、リアルな意見交換を行うなど、現場の課題を実感できる機会を併せて提供することで、管理職だけではなく部下にとっても相手のことを理解できる環境を整えることができます。
さらに、指示型のコミュニケーションから、質問型のコミュニケーションへ移行することで、部下は「私のことを理解しようとしてくれている」と感じることができるでしょう。相互理解が深まり、コミュニケーションが促進されることで、柔軟な発想や新しいアイデアが出やすい環境を整えることが出来るようになります。
前編では「急速なビジネス環境の変化」「部下とのコミュニケーション不足」「ジェネレーションギャップの拡大」という3つの課題を解決するための研修施策について取り上げました。管理職の能力を最大化させるために「今」必要な5つの対策(後編)では「教育・指導スキルの不足」「自己研鑽の時間と費用の不足」について考えていきたいと思います。